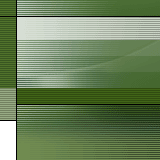
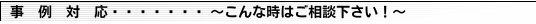
簡単な回答は後記にあります。詳しくは電話にてお尋ね下さい。
〔電話対応時間:平日9時から5時まで〕
Q① 親が亡くなって、土地や建物の名義を書き換えないといけないんだが、手続きがよく分からないな。又、費用は幾らぐらいかかるのかな?【回答】
Q② 親が亡くなって遺産がかなりあるんだけれど、どうすればいいのかな。他県にも不動産があるし。又、相続税はどうなるのかな? 【回答】
Q③ だいぶ昔に亡くなったお祖父さんの名義の不動産があるんだけれど、相続人が誰になるのかハッキリ分からないな。どうすればいいだろうか? 【回答】
Q④ 家を新築したんだけれど、何か登記をするのかな? 【回答】
Q⑤ 家を増築したんだけど、父親の家に息子の私が資金を出して増築したんだよ。このままでいいのかな? 【回答】
Q⑥ 親(あるいは兄弟)の土地の一部を貰って、そこに家を建てたいのだけれど、どうしたらいいかな?税金の問題は? 【回答】
Q⑦ 夫婦間贈与をして、相続税の負担を減らしたい。 【回答】
Q⑧ 隣家との境界が曲がっているのでお互い使いやすくするために、土地の交換をしたいんだけど、面倒かな? 【回答】
Q⑨ 知り合い同士だったので、仲介さんを通さないで土地・建物を売買する(した)んだけれど、 手続きはどうすればいいのかな? 【回答】
Q⑩ 銀行のローンを返し終わって書類を貰った。早く抵当権を抹消したい。 【回答】
Q⑪ 引っ越しをしたが、土地の名義の住所が元のままだ。現住所に直した方がいいのかな?
【回答】
Q⑫ 会社を設立したい。どうすればいいのか?費用はどのくらいかかるのかな?
【回答】
Q⑬ 法人の役員が代わったんだけれど、登記をするのかしら? 【回答】
Q⑭ 法人の所在が移転したんだが、登記をするのかな? 【回答】
Q⑮ 親が年をとって認知症になってしまった。子の私が親の財産を処分できるのかしら? 【回答】
Q⑯ 自分が元気なうちに、「自分が年をとって判断能力が無くなった時に自分の財産をしっかり管理してくれる人を確保しておく」制度があると聞いたけど、どうすればいいのかしら。 【回答】
Q⑰ 妻にしっかり私の財産を残したいので遺言を書きたい。どうすればいいだろう。 【回答】
Q⑱ 遺言で、私が故人の遺産を取得することになったのだけれど、相続人が多数で財産も複雑だわ。どうしましょう。 【回答】
Q⑲ 以前亡くなった私の叔父の連れ合い(義理の叔母)が最近亡くなりました。年を取ってから、私がずっと面倒を見ていました。義理の叔母、子も兄弟もいないんですね。それなりに遺産があるんですが、どうなるんでしょうね? 【回答】
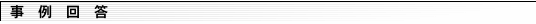
A① 不動産の名義は、常に生きている人のものでないと色々な不都合が生じます。
法定相続人(権利のある人)が数名いる場合は、通常、遺産分割協議をして、特定の相続人を決めて、その人に、正確に言うと「相続による所有権移転登記」を行います。
費用は様々ですが、フツーの土地・建物あるいはマンションを相続した場合、10万から20万円ぐらいで収まります。
A② 遺産が多い場合は、相続税の問題が生じます。ご安心下さい。そういう場合は、信頼できる税理士を紹介します。この税理士と連絡を取り合いながら仕事を致します。又他県の不動産も大丈夫です。我々は全国ネットワークを持っています。
A③ 古い相続はなかなか難しい面があります。相続人を確定する作業と更に確定した相続人が協力してくれるかどうかという問題です。人の心までは分かりませんから。
この場合、当事務所は、相続人の確定から始め、確定した相続人の方にも、なるべく詳しい資料を提供するよう心掛けております。隠さないことですね。
A④ 家を新築すると、まず表題登記というものを掛け、次いで権利の登記をします。表題登記は土地家屋調査士が行います。この調査士も当事務所にて手配できます。
A⑤ 親の建物に、子が自らの資金を投じて増築をした場合、何もしないと子から親への贈与となり、贈与税の対象になります。増築部分は家としての独立性がない為、親がポンと貰ったのと同じです。こういう場合、状況に応じて何通りかの手法があります。当職が何度も経験した登記です。
A⑥ まず土地に線は引いてありませんから、分筆の登記をします。つまり土地を図面の上で切るのですね。この仕事は土地家屋調査士の仕事です。この場合、信頼できる土地家屋調査士を当職が責任を持って紹介します。分筆が終わったら贈与の登記をします。贈与税の問題が生ずる場合があります。早速、税理士と打ち合わせをして、依頼者にいくつかのシュミレーションを提示して登記を進めます。
A⑦ 20年以上の夫婦間の居住用財産の贈与は2000万円まで(正確には2110万円まで)贈与税が掛かりません。この手続きもよくあることです。
A⑧ この場合も、境界をまっすぐにして出っ張ったり引っ込んだりした部分を互いに交換するのですね。土地家屋調査士と連絡しながら進めます。
A⑨ 仲介を通さない売買の場合、以下のポイントがありますが、当事務所は、これらを全て行います。
・契約書の作成
・売買代金の支払及び書類の授受への立会
・固定資産税の精算等
A⑩ 抵当権の抹消はバカになりません。放って置くと抹消が難しくなったり、予想外の手間と費用がかかる場合があるからです。金融機関から書類を貰ったらなるべく早く抹消しましょう。典型的な土地・建物1個ずつの例で大体、1万円ぐらいです。外に印紙代2000円が掛かります。抹消後の登記簿謄本を取得したいのなら別途費用が掛かります。尚、当事務所は乙号オンラインに対応しています。
A⑪ 住所変更の登記も放っておくと、住所がつながらなくなり手間が掛かります。早めに済ませましょう。抹消と同じ例で、抹消より2000円位安めです。
A⑫ 会社の設立は、有限会社は出来なくなりました。株式会社が主ですね。当事務所は電子認証対応です。紙申請より40000円安くなります。資本金1000万円を前提にすると費用は全部で大体32万円から35万円ぐらいで出来ます。
又、今後ずっとお付き合いすることになりますが、依頼者に税理士の知り合いがいない場合は当事務所にて紹介できます。
A⑬ 役員変更も放っておくと罰金を取られる場合があります。当事務所は責任を持って、役員改選の時期が近づいた法人には連絡致します。
A⑭ 法人の所在が変わった場合も登記をしなくてはいけません。県外でも簡単に出来ます。
A⑮ この場合、子だからといって親の財産を勝手に処分することは出来ません。基本的には「成年後見人」を家庭裁判所に選任して貰います。もちろん家族がこの後見人になれます。家族がなり辛い事情がある場合、第三者である司法書士がなることも出来ます。ご安心下さい。松原は法務大臣から認可を受けた成年後見センターリーガルサポート(略してリーガルサポート)の社員であり、又、家庭裁判所に名簿登載されております。安心して御依頼下さい。
A⑯ このような場合、任意後見契約を公正証書にて締結します。「私が判断能力が無くなったらあれこれしてください」という内容の契約を詳細な代理権目録を付けて結ぶのです。もちろん当職が受任者になるか、あるいは依頼者にふさわしいリーガルサポートの会員を推薦します。
A⑰ 遺言作成は当職の得意分野です。必ずや依頼者のニーズに応じたメニューを用意します。
A⑱ こういう場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任して貰うと、手続が進みます。もちろん指名されれば、私が執行者になります。
A⑲ この場合法定相続人がいないので、そのままでは、義理の叔母の遺産は、国有財産になります。そこで、まず相続財産管理人を、家庭裁判所に選任して貰う。次に、この「私」を、特別縁故者ということで申立をすると、遺産の引渡を受けることが出来る場合があります。